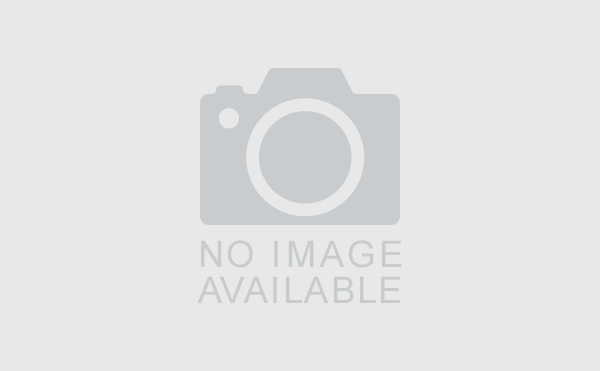松井宏光先生 ~2011年10月8日「森へ出かけましょう」講師
「子どもたちに明るい未来をNETを支えてくださる方々」シリーズ
第三回目は、10月8日のイベント「森へでかけましょう」の講師
松井宏光先生をご紹介します。
松井先生は、今年度のイベントには、
なんと「バスガイド」としてご参加くださいます。
今回は久万高原町が、町所有のバスを出してくださるので
町内(天体観測館~面河山岳博物館)をバス移動するのですが
片道40分をせっかくなので、森生学がご専門の松井先生に
レクチャーしていただこう、とお願いしました。
定員40名ですが、大変贅沢なイベントになっています。
松井先生は、愛媛新聞をご購読の方はご存知、「四季録」の執筆者でもあります。
森や自然のお話が、興味深く、また叙情的な文章で大変好評を博しているそうです。
***プロフィール****
広島大学理学部生物学科植物学専攻。
学生時代はワンダーフォーゲル部で自然に親しむ。
松山東雲短期大学教授。専門は植物学・環境教育。
「愛媛の薬用植物図鑑」「愛媛の自然をたずねて」
(共著・愛媛出版文化賞受賞)
「石鎚山系自然観察入門」(共著)
「愛媛の人里野草図鑑」(共著、愛媛出版文化賞受賞)
「愛媛の巨樹、名木」(編著)など多数。
*************
来年2月に私たちが主催するシンポジウムの
コンセプトについてご相談したときのお返事です。
と~ってもロマンチストの松井先生が垣間見られる文章です。
進化しつづける科学技術、
自然がなくても快適な都市での生活、自動車でどこでもお出かけ、
調理も空調も電気製品でとても快適、
だけどガソリンが電気の供給が途絶えたら・・・
季節を問わず年中手に入る食材、世界中から届く日常の物品
だけど交通網が途絶えたら・・・
自然災害や原発事故が科学技術に支えられた
依存した都市の快適生活の危うさを示した
田んぼと畑が広がる農村で、自分の食べる野菜やコメを栽培し、夜は涼しく
でも田舎暮らしは老人か、自然志向か芸術家の変わり者の若者夫婦。
現金収入、教育、医療を考えたら、やはり田舎暮らしは難しい。
ツタヤも明屋も、ユニクロもコンビニも、至近距離になくてもいいけど、
どこかには必要だろう。ネット環境も必要だろう。
自動車も学校も病院もスーパーも必要だけど。
楽しく住める町とはどんな町だろう。
みんなで住んでみたい町づくり。
不便に耐えるのではない町とは?井上