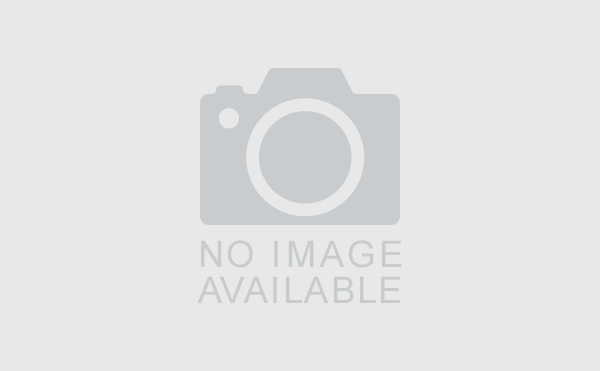苦しみを分かち合うために
東日本大震災から半年が過ぎました。
西日本の私達が、東日本で被災された方々のために出来ることは何でしょう?
現地でボランティアをしたり、義捐金を送ることは直接的に
とてもお役に立つことだと思います。
節電意識も高まってきました。
しかし、経済復興のために、西日本は元気に消費してほしい、と
東日本の人が言っているから、しょんぼりしないでどんどん今まで通りの
消費型生活をしよう、という声もよく耳にします。
3月11日以来、イベントを実施する団体のほとんどが
収益の全額または一部を義捐金として寄付をすると表明しています。
極端にいうと1000円でも「一部」です。
私たちも、10月にイベントを控え、東日本大震災への思いを
どのように形にしていくべきか、考えました。
そして私なりに出した「答え」は、東日本、いえ日本が元気になるためには
私達が、今まで通りであってはいけないと思うのです。
生物として、社会的存在としての成長を遂げなければ
この国難は乗り切れないのではないかと思うのです。
そのためには、「収益の一部を寄付すること」よりも
「参加された方々の成長に貢献できるような内容にすること」を
目指したいと思うのです。
自然体験学習や、写真家の星野道夫さんや松本紀生さんの写真を鑑賞したり
生の音楽を鑑賞することを通して
自然を畏れ敬う心や、消費型アミューズメントパークに行かなくても
感動や喜びを感じられることを知っていただき
便利なことや楽をすることを求めるのではなく、額に汗して
世の中のために働き、今ある中から希望を見つける喜びを感じてもらいたいと思います。
これからは、有名大学の卒業証書より
自然の中で何も無くても「何ができるか」、が問われる時代になると思います。
電気が来ないと鳴らない楽器よりも、電気が無くても奏でられる楽器や、
歌うこと、踊ること、そういう楽しみを、より多くの人に知っていただきたいと思います。
あなたの成長が地球環境を変える! 立山祐二著
この本は、2004年7月9日に出版されています。
出版から7年。私達は果たして成長してきたのでしょうか?
冒頭に1995年1月8日付け神戸新聞の記事が掲げられています。
阪神大震災の直前です。
3面にかなり大きな取り扱いであるにもかかわらず
ほとんどの人が、気づかなかった、知らなかったと答えているそうです。
このことを、立山氏は「カクテルパーティー現象」として
「見たくないことは見ない」「聞きたくないことは聞かない」
「存在しないと信じていることは見えない」
つまり、「関心のあること」しか感知しないと分析しています。
私達の小さな活動も、「関心の無い」人に「関心を持ってもらう」ことを
目指していけば、意味があると思うのです。
立山氏は、「個人的成長が環境問題を解決する」「まず自分が変わる」と
提言されていますが、(2004年に)
個人も成長せず、環境問題も悪化の一途をたどっています。
引用されている、この記事、2003年の記事ですが
原発に頼らざるをえない状況にしたのは誰か、
我慢のない国民・・・という構図も指摘されながら少しも反省せず、
多くの識者が電力に頼りすぎた国民生活に危惧を唱えてきましたが
その声が、国民の耳に届かないまま壊滅的被害まで突き進ませてしまいました。
この本を読んだ人が何人いるのかわかりませんが、
国民の生命に危機が及ぶまで、反省し、生き方を変えることができなかった
私達ですが、今からでも、生き方を変えていかなければ
生きる道はない、と思うのです。
人を変えようとは思っていません。
そんなことは出来ません。
ただ、一人ひとりの人が自然の美しさや偉大さ、音楽や映像を楽しむ
生き方を選択するチャンスになればと願っています。
この本の最後には、人というものについて書かれています。
「助けられ、助け、そして助けられる」
子供時代は助けてもらい、成人すれば助け、老人になれば助けられる
という構図の他に、思いがけない事故や天災で助けを必要とする人を
助けられる人が助ける、その立場は常に変化する、と書かれています。
西日本の私達は、今こそ、助ける立場にあります。
明日は助けてもらう立場になるかも知れませんが、助けることができる
喜びを、教えてもらえる本でもあります。
井上